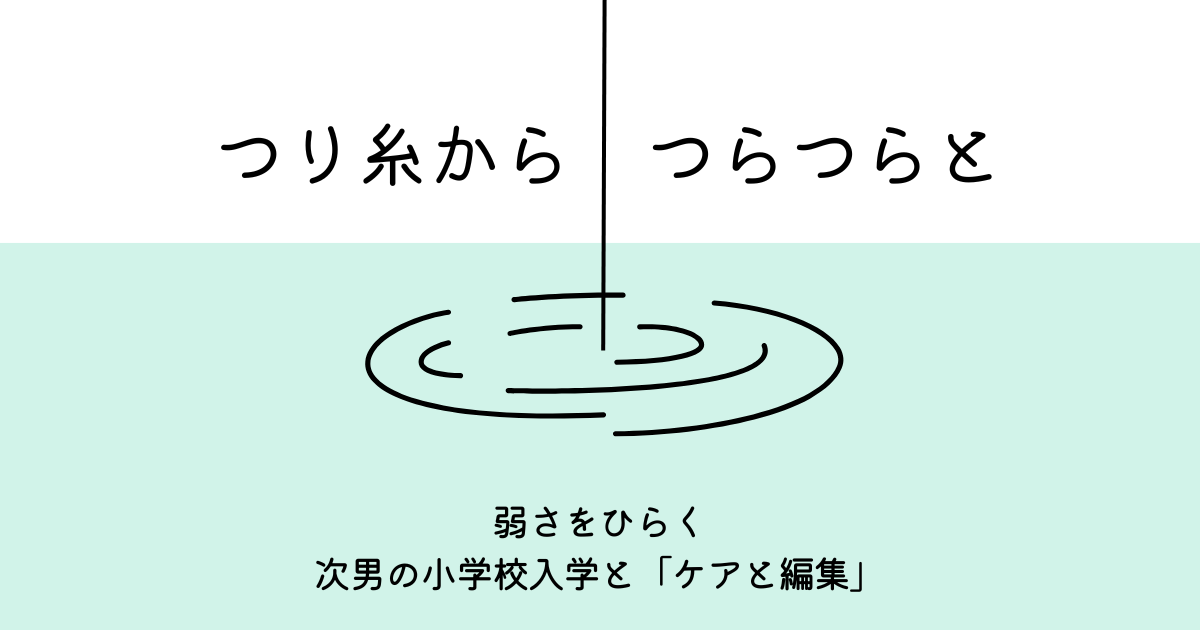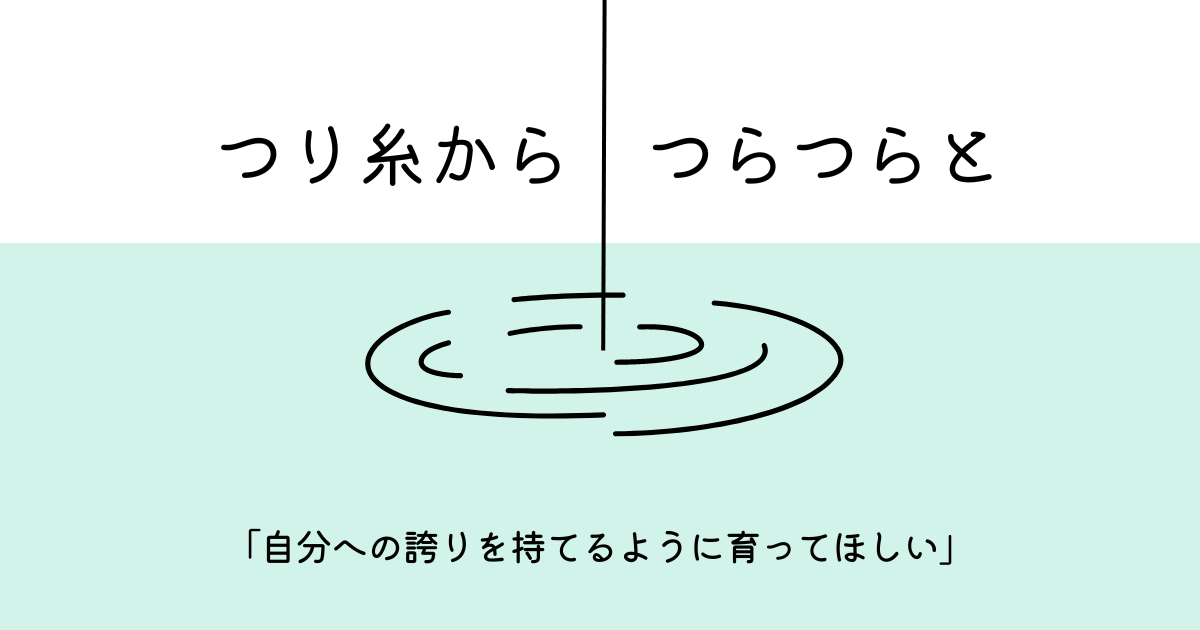この春、我が家では、次男が小学校に入学しました。
「小学生」のタイトルに、緊張しながらも張り切っていたのは最初だけ。
新しい環境、新しいお友だちや先生たち、決められた時間に決められたことをやる新しい制度になかなか馴染めず、「学校行きたくない」と泣く日々が続きました。
わたし自身も、そんな息子に振り回されて、落ち着かない日常に疲れていました。
このごろになってようやく、次男は「小学生」に慣れてきて、わたしも気楽でいい加減な気持ちで彼を送り出すことができるようになってきました。
学校に通って「よい子」になるなんて全然大事なことだと思わないけれど、学校は出会いの場だから。恐る恐るぶつかってみたら、何かに出会い、何かしら彼を育んでくれるかもしれない。
ただ、学校しかないわけでもなければ、今しかないわけでもない。
「その程度のこと」と思いながら背中を押す塩梅は、がんばってしまうとできない構えのような気がしています。
子どもはすごいなと思うのは、自分の弱さ全開ですがってくるところ。
「いやだ、できない、こわい、行きたくない」
目の前でこう言いながら大泣きされたら、こちらも放っておけない。事態に巻き込まれてしまう。
大泣きまではしなくとも「できない」と言うこと自体が、「自分は一人前です」って思って生きてる大人たちには、なかなかできないことではないでしょうか。
最近読んだ、白石正明さんの『ケアと編集』(岩波新書)という本に、「弱いロボット」の話が紹介されていました。
豊橋技術科学大学の岡田美智男さんが作るロボットは、誰かの助けがないとなにもできない不完結・不完全なロボット。
例えば、ゴミ箱型の「ゴミ箱ロボット」は、ゴミを見つけることはできるけれど、自分で拾うことはできない。彼がゴミの近くでまごまごしていると、通りかかった人がつい代わりにゴミを拾って投げ入れてくれる。
この自己完結できない「弱さ」には、人を巻き込みながら物事を成し遂げる力がある。
この「弱さ」は、関係性のなかで生きている存在にとって、とても根源的で大切な力なんじゃないかと思います。
また、この本には、熊谷晋一郎さんの「多くの人や物に依存できることが自立の条件である」という言葉も紹介されていました。
自立というのは、依存を克服した状態ではなく、依存先を増やして分散させることで「自分は何にも依存していない」と感じられる状態である、とのこと。依存先が集中すると、それを失ってしまう恐れにより、支配ー被支配関係につながることもある。
先日、次男の担任の先生から「最近よく『学童行きたくないわー』って言ってます」と聞いて、「先生に弱音を吐けるようになったんだな」と安心するとともに、「次男よ、順調に依存先を増やしてるわね!」と嬉しくなったのでした。
「弱さ」は「強さ」に、「依存」は「自立」に、克服し、書き換えられるべきものと考えられがちではないでしょうか。そこには、「現在を否定して、さらに善きものに改変しなければならない」という前提があります。
この本を通じて著者の白石さんは、ケアとは何かという問いに「それ自身には改変を加えず、その人の持って生まれた〈傾き〉のままで生きられるように、背景(言葉、人間関係、環境)を変えること」とこたえています。そして、「本来的に善き方向に向かおうとしているが、それを邪魔している要素があるからうまくいかない」というケア論的前提を、「すでにして完全」と表現しています。
このケア論的まなざしは、子どもたちにはもちろん、大人たちにももっと向けられていくべきものじゃないかと思います。コーチングって、きっとそのためにあるんじゃないかなってわたしは思っています。
そして最後に、この本のとてもいいなと思うところは、ケアする人のことを「太陽や空気や地面と同じように、この世界をどうにか存続させている基底的な条件」だといっていること。今この瞬間も、無数のケアする人たちが世界のほころびを手入れしているからこそ、「今、ここ」は成立している。
そういう目立ちにくい、当たり前になっている存在たちに、感謝とねぎらいの気持ちを忘れないでいたいですね。
いや、本音を率直に言うと「息子たちよ、母の存在を当たり前に思うなよ!」だな。笑
わたしを含めた数多のケアする人たちに、心からの感謝とリスペクトを!今日も世界を存続させる偉大なお仕事、大変おつかれさまです。

*
みみをすますラボでは
あなたと わたしが みみをすまし
ふれあい、うつしあい、ひびきあう、
そんなコーチングを提供しています。
あなた自身に、あなたの世界に、一緒にみみをすますことから始めませんか?
お気軽に、まずは体験セッションからお申込みお待ちしています^^